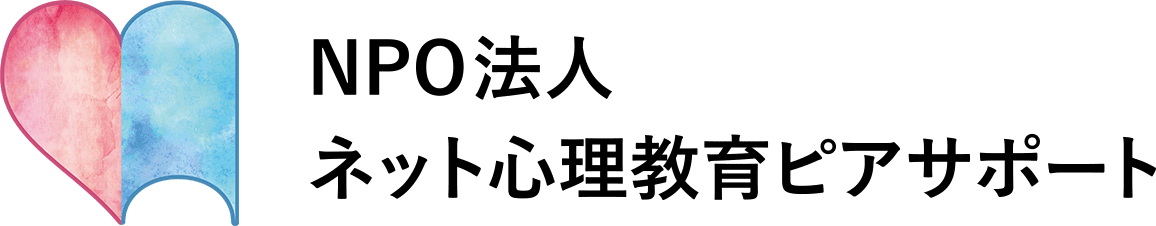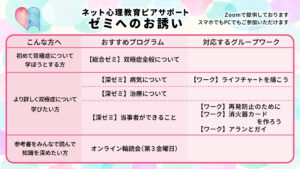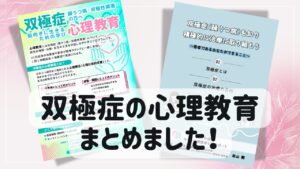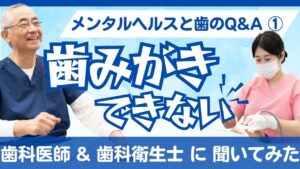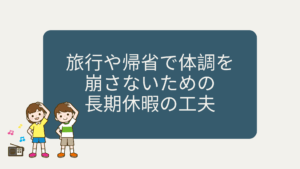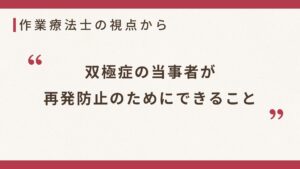お盆明け、ちょっと元気すぎ?「躁かも」と思ったときの対処法
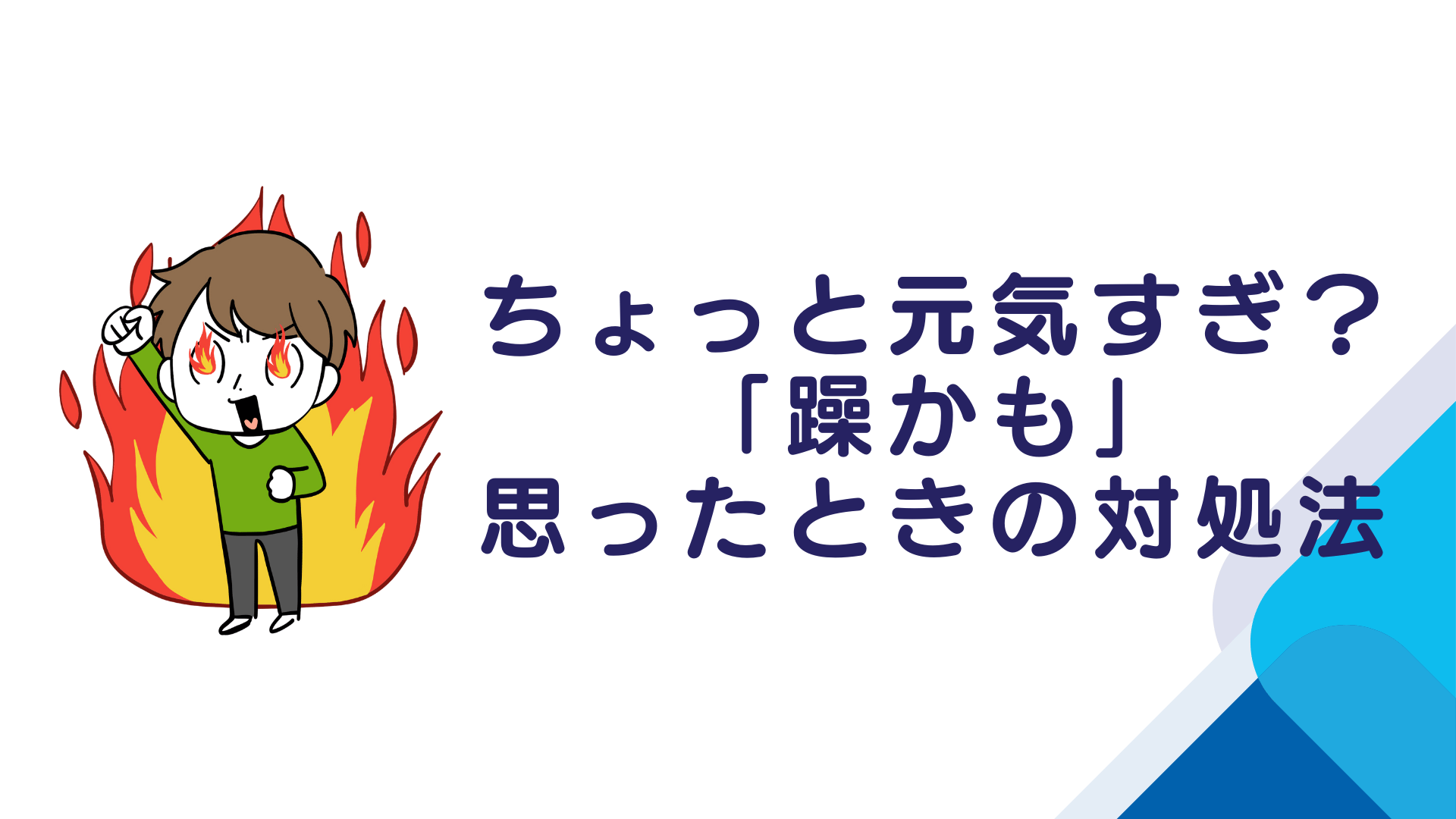
 おと
おと双極症Ⅱ型当事者、作業療法士のおとです。
お盆などの長期休暇が終わると、また日常生活が戻ってきますね。
「よし、今日からまた頑張ろう!」と気合が入るのはいいことです。
ですが、ちょっと元気すぎるな?と感じたら、それは「躁っぽさ」のサインかもしれません。
今回は、【長期休暇明けに“気分が上がりすぎてしまう】とき、どんなことに気をつけたらよいかをお伝えします。
なぜ休暇明けに「躁」に注意が必要?
双極症というと、うつ状態のつらさが注目されがちですが、実は「躁状態」も見過ごせない問題です。
長期休暇明けは、
・テンションが高くなりやすい
・楽しいイベントや旅行の余韻がある
・やるべきことが溜まっていて焦る
といった状態になりやすいです。
知らず知らずのうちに活動量やテンションが上がり、「軽躁状態」に突入してしまうケースがあります。
こんな行動が出ていたら要注意かも?
以下のような変化がある場合は、軽躁の入り口かもしれません。
「元気になっただけ」と思いがちですが、こうした変化が続くと一気に波が崩れ、後にうつへ反転する可能性もあります。
やることは7割にとどめる
調子がいいときほど、「よし、いろいろ取り戻すぞ!」とフル回転したくなりますが、それは体調管理の面では危険信号。
私は「やることリスト」は作っても、実行するのは“7割”までと決めています。
「まだできるのに、物足りない…」と感じるかもしれません。
でもその“物足りなさ”こそが、今の自分にブレーキをかける重要なサインです。
「物足りない」は悪じゃない、むしろ味方
元気なときに100%の力で動いてしまうと、後になって疲れや寝不足がたまり、
結果として「軽躁→反動でうつ」という流れにハマってしまうことがあります。
あえて余裕を残すことで
・疲れが溜まりにくい
・睡眠が安定する
・翌日も安定して過ごせる
といった大きなメリットが得られるのです。
私も昔は「できるうちにやらなきゃ」と焦っていましたが、
今では「やりすぎないこと」がむしろ病気と上手く付き合うコツだと感じています。
7割で抑えるためのちょっとした工夫
- TODOリストは最大3つまで
- スケジュールに「空白時間」を意識して入れる
- 「終わってないけど、今日はここまで」と区切る
- できなかったことを責めない
「余裕を残すこと」は怠けることではなく、未来の自分のための準備です。
特に、頑張りすぎて調子を崩しがちな方ほど、この7割ルールは効果的です。
活動量・睡眠・記録で自分を整える
躁のサインに気づくには、「自分の変化に気づける仕組み」が必要です。
特に大切なのが次の3つです。
- 活動量のチェック
→ 歩数や外出頻度、会話の多さなどを振り返る - 睡眠の記録
→ 「寝つき・途中覚醒・睡眠時間」をざっくりでも記録 - 気分の記録
→ 1日1回、-2(うつより)~+2(躁より)で簡単に気分チェック
周囲と連携して気づける工夫
もし信頼できる家族やパートナー、友人などがいれば、
「最近ちょっと元気すぎたら教えて」とあらかじめ伝えておくのも有効です。
自分では「今ちょうどいい」と思っていても、他人から見るとテンションが高すぎたり、会話が早口になっていたりすることがあります。
おわりに|物足りないくらいが、ちょうどいい
お盆明けなどの休暇後、「元気が出てきた」と思えるのは素晴らしいことです。
でも、その“元気”が少し突き抜けていたら、
「今、ちょっと気をつけたほうがいいかも」と、立ち止まってみてください。
物足りない=うまくいっている証拠かもしれません。
焦らず、ゆっくり、ほどほどに。
無理のない範囲で長期休暇を過ごし、病状の安定に努めていきましょう。
注意事項
※本コラムは、双極症に関する経験や知識をもとに執筆されたものであり、すべての方に当てはまる内容ではありません。
個別の診断や治療については、必ず主治医等の専門家とご相談ください。
以上
さらにキーワードで検索したい方はこちら!