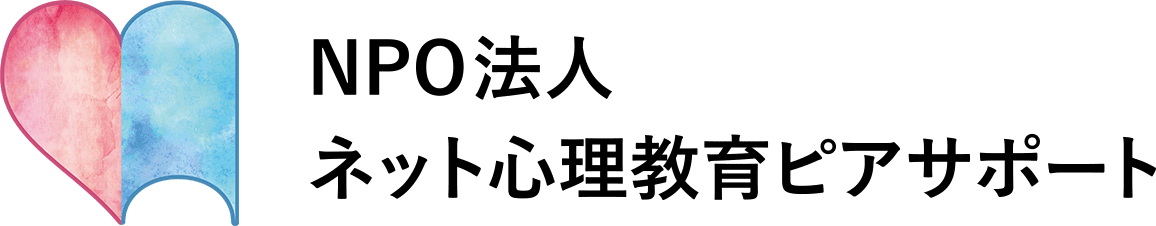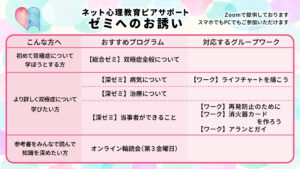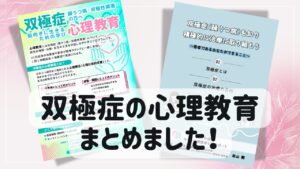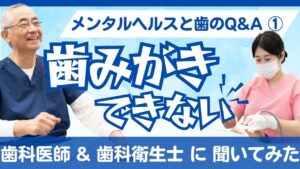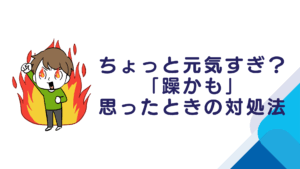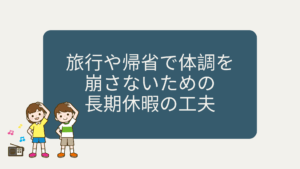双極症と就業形態:当事者のための包括的ガイド
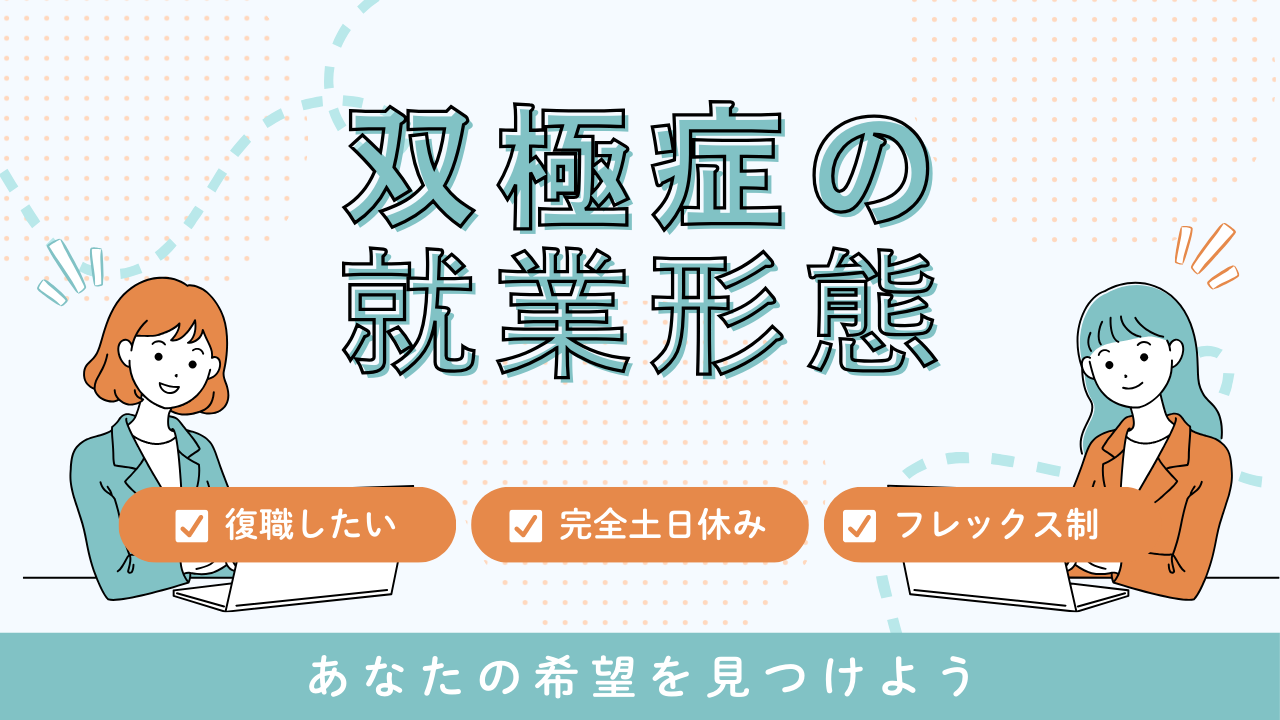
はじめに:双極症当事者の職業選択について
双極症(双極性障害)を持つ私たち当事者が職業を選択する際には、特有の配慮が必要です。この記事では、双極症を抱えながら社会で活躍するための多様な就業形態とその特徴を解説します。
私自身も双極症と診断され、休職後職業探しをしました。職務経歴書を作成したり、自分の症状管理と将来の目標に合う働き方を考えました。その情報を同じように悩む方々のためにまとめました。
双極症当事者のための就業選択の重要ポイント
1. 症状の波に対応可能な柔軟性
双極症の特徴である躁状態と鬱状態の波に対応できる柔軟な勤務体制が理想的です。在宅勤務やフレックスタイム制度が整っている職場では、調子が優れない日でも自分のペースで働くことができます。症状の波に合わせて業務内容や量を調整できる環境が望ましいでしょう。
2. ストレス要因への対処
職場のストレスは双極症の症状を悪化させる主要因です。特に人間関係のストレスは症状の引き金になりやすいため、個人作業が中心の職種や人間関係がシンプルな環境が望ましい場合があります。また、通勤時間や通勤手段も重要な要素です。
3. 収入の安定性
経済的な不安定さは双極症の症状を悪化させる要因となります。安定した収入があることで、治療費の確保や生活の安定が図れ、精神的な安定にもつながります。福利厚生が充実している企業も、双極症当事者にとっては大きなメリットとなります。
就業形態の詳細
クローズ就労:障害を非開示で働く道
クローズ就労とは、双極症を企業や同僚に開示せず、一般の方と同じように働く形態です。この選択肢は、障害に関する偏見や差別を避けたい方や、自分の能力を最大限に発揮したいと考える方に適しています。
クローズ就労の最大のメリットは、職種や業界の選択肢が広がることです。障害を開示することで閉ざされる可能性のあるキャリアパスも、クローズ就労であれば挑戦することができます。また、一般の雇用枠で働くことで、給与水準も比較的高くなる傾向があります。偏見や差別を受けるリスクが少なくなるため、純粋に能力や実績で評価されることができるのも魅力です。
一方で、クローズ就労には大きな課題もあります。症状が悪化した際に適切な配慮を受けられない可能性があることや、常に症状を隠す精神的負担が生じることなどです。特に、通院や服薬のための時間確保が難しい場合もあります。また、長時間労働や高ストレスの職場環境は、症状の悪化につながる可能性もあります。
クローズ就労を選択する場合は、自己管理能力が非常に重要になります。症状の変化に早めに気づき、適切な対応を取る自己観察力や、ストレスマネジメント技術を身につけておくことが必要です。
オープン就労(一般雇用):障害を開示しながら一般枠で働く
オープン就労(一般雇用)とは、双極症を企業に開示しながらも、一般の雇用枠で働く形態です。この選択肢は、障害への理解と配慮を得つつも、一般枠での幅広い業務や責任を担いたいと考える方に適しています。
この就労形態の大きなメリットは、障害への一定の配慮を受けながらも、一般枠での雇用のため、業務範囲が広く、給与水準も比較的高いことです。障害を開示することで、通院のための休暇取得や、症状に合わせた業務調整など、必要な配慮を受けられる可能性があります。また、能力や実績によって昇進や昇格の機会もあり、キャリアアップを目指すことも可能です。
しかし、課題もあります。一般雇用枠のため、障害者雇用枠と比べると配慮の程度が限られる場合があります。また、採用時には理解を得られても、人事異動や組織変更などで上司や同僚が変わった際に、改めて理解を得る必要が生じることもあります。さらに、職場によっては障害に対する理解不足から、不適切な対応を受ける可能性もあります。
オープン就労(一般雇用)を選択する場合は、自分の障害について適切に説明できるコミュニケーション能力と、必要な配慮を具体的に伝える自己擁護スキルが重要になります。
オープン就労(障害者雇用):特性を活かす専門枠での就労
オープン就労(障害者雇用)とは、障害者手帳を取得し、企業の障害者雇用枠で働く形態です。この選択肢は、自分の障害特性に合わせた配慮を受けながら、長期的に安定して働きたいと考える方に適しています。
障害者雇用枠での就労の最大のメリットは、障害への理解と配慮が得られやすいことです。通院のための休暇取得や、症状に合わせた業務調整など、双極症の特性に配慮した働き方が可能になります。また、法定雇用率の対象となるため、企業側も継続的な雇用を前提としており、長期的な雇用安定が期待できます。
職種も多岐にわたり、一般事務だけでなく、システムエンジニア、Webデザイナー、データ入力、軽作業など様々な選択肢があります。特に近年は、障害者の特性を活かした専門職の採用も増えています。例えば、双極症当事者の中には、躁状態時の創造性を活かしたクリエイティブ職や、細部への注意力を活かした校正・チェック業務などに適性を持つ方もいます。
一方で、障害者雇用枠での就労には、給与水準が一般雇用に比べて低い傾向があることや、業務内容が限定される場合があるといった課題もあります。また、「障害者」というラベルからくる周囲の先入観や、自己アイデンティティへの影響に悩む方もいます。
障害者雇用枠での就労を選択する場合は、障害者手帳の取得や、ハローワークの専門窓口への登録など、必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。
A型作業所(就労継続支援A型):雇用契約に基づく支援付き就労
A型作業所(就労継続支援A型)は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、一般企業での就労が困難な障害者に対して、雇用契約を結んだ上で就労機会を提供する場です。この選択肢は、一般企業での就労に不安がある方や、段階的に就労経験を積みたい方に適しています。
A型作業所の大きな特徴は、福祉サービスでありながら、雇用契約に基づく「賃金」が支払われることです。最低賃金が保障され、社会保険にも加入できるため、一定の経済的安定が得られます。また、障害への理解が前提となっているため、症状に合わせた配慮や支援が充実しています。作業環境も比較的ストレスが少なく、双極症の症状管理がしやすい環境が整っていることが多いです。
A型作業所で行われる仕事は、軽作業や清掃、データ入力、事務作業など様々です。近年では、IT関連業務やデザイン業務など、専門性の高い仕事を提供するA型作業所も増えています。また、一般就労への移行を目指す方のためのスキルアップ研修や、就職支援も行われています。
一方で、A型作業所での就労には、給与水準が一般企業と比べて低い傾向があることや、仕事内容が限定的である場合が多いといった課題もあります。また、「福祉的就労」というイメージから、キャリアアップの機会が限られると感じる方もいます。
A型作業所を利用するためには、市区町村の福祉窓口での手続きや、障害者手帳の取得、障害支援区分の認定などが必要です。事前に見学や体験利用ができる場合も多いので、自分に合った作業所を探す際には積極的に活用することをお勧めします。
B型作業所(就労継続支援B型):福祉的支援を受けながらの就労
B型作業所(就労継続支援B型)は、A型と同じく障害者総合支援法に基づく福祉サービスですが、雇用契約を結ばず、より福祉的な側面が強い就労支援サービスです。この選択肢は、症状が比較的重く、一般就労やA型作業所での就労が難しい方に適しています。
B型作業所の最大の特徴は、雇用契約ではなく「工賃」という形で報酬が支払われることです。そのため、働く時間や日数を自分の状態に合わせて柔軟に調整しやすいという大きなメリットがあります。特に双極症のように症状の波がある場合、調子の良い時には多く働き、調子が悪い時には休むといった調整がしやすい環境です。
また、B型作業所では福祉的な支援が充実しており、生活面でのサポートや、医療機関との連携も図られています。作業内容も個人の能力や状態に合わせて調整されるため、無理なく取り組むことができます。近年では、オンラインでの作業を取り入れるB型作業所も増えており、通所が難しい方でも利用しやすくなっています。
一方で、B型作業所での工賃は非常に低く、平均月額は1〜2万円程度であることが多いため、経済的な自立は難しいのが現状です。多くの利用者は障害年金と組み合わせて生活しています。また、一般就労への移行を目指す場合、スキルアップや就労経験の面で限界を感じることもあります。
B型作業所を利用するためには、A型と同様に市区町村の福祉窓口での手続きが必要です。また、地域によって提供されるサービスの内容や質に差があるため、複数の作業所を見学・体験してから選択することをお勧めします。
フリーランス(個人事業主):自分のペースで働く独立の道
フリーランス(個人事業主)として働くことは、双極症当事者にとって一つの魅力的な選択肢となり得ます。この働き方は、自分のスキルや専門性を活かしながら、自分のペースで働きたいと考える方に適しています。
フリーランスの最大のメリットは、働く時間や場所、仕事の量を自分で調整できる高い自由度です。双極症の症状に合わせて、調子の良い時には集中的に仕事をし、調子が悪い時にはペースを落として休むといった柔軟な働き方が可能です。また、オフィス環境からくるストレスや人間関係の煩わしさから解放されることで、精神的な負担が軽減されることもあります。
特に、Webデザイン、プログラミング、ライティング、翻訳、イラスト制作など、在宅でも取り組めるクリエイティブな仕事は、双極症当事者のフリーランスとして適している場合が多いです。これらの職種は、双極症の躁状態時に高まる創造性を活かせる一方で、納期の調整が可能な案件も多く、症状の波に対応しやすいという特徴があります。
一方で、フリーランスには収入の不安定さというリスクがあります。特に、仕事の受注が安定するまでは経済的な不安を抱えることも多く、それが精神的なストレスとなって症状を悪化させる可能性もあります。また、自己管理能力や営業力、専門スキルなど、一人で仕事を回していくための能力が求められることも課題となります。
フリーランスとして働く際には、安定した顧客基盤の構築や、複数の収入源の確保など、収入の安定化を図る工夫が重要です。また、確定申告や健康保険、年金などの手続きも自分で行う必要があるため、事前に知識を身につけておくことも大切です。
起業:自分の夢を形にする挑戦
起業は、自分のアイデアやビジョンを形にし、自分らしい働き方を追求できる選択肢です。この道は、強い情熱や明確なビジョンを持ち、リスクを取りながらも自分の夢を追求したいと考える双極症当事者に適しています。
起業の最大のメリットは、自分の価値観や理念に基づいたビジネスを展開できる創造的な自由度の高さです。自分が理想とする職場環境や働き方を自ら創り出すことができるため、双極症の特性に合わせた働き方を実現しやすいという利点があります。例えば、自分の体調に合わせて柔軟に働ける環境を整えたり、双極症の経験を活かした商品やサービスを提供したりすることも可能です。
また、起業することで得られる達成感や自己実現の機会は、双極症当事者の自己肯定感や生きがいの向上につながることもあります。特に、これまで社会での居場所を見つけられなかった方にとっては、自分の居場所を自ら創り出す機会となり得ます。
一方で、起業にはリスクや負担が大きいことも事実です。特に立ち上げ期には長時間労働や高ストレスの状況に陥りやすく、それが双極症の症状を悪化させる引き金となる可能性もあります。また、経営の不安定さや責任の重さが精神的な負担となることも少なくありません。
起業を考える際には、自分の症状管理能力を正確に把握し、無理のない計画を立てることが重要です。また、共同創業者やビジネスパートナー、メンターなどのサポート体制を整えることで、負担を分散させることも検討しましょう。さらに、小規模から始めて段階的に拡大していくなど、リスクを最小限に抑える戦略も有効です。
就業手続きのポイント
双極症当事者がそれぞれの就業形態を選択する際には、障害者手帳の取得や各種支援制度の利用方法など、必要な手続きを理解しておくことが重要です。特に障害者雇用や福祉的就労を選択する場合は、地域の支援機関やハローワークの専門窓口を活用することをお勧めします。
まとめ
双極症と共に働くには「生活の安定」と「やりがい」という二つの要素が重要です。自分の症状の特徴や生活スタイル、キャリア目標に合わせて最適な就業形態を選択し、自分らしいライフキャリアプランを実現していきましょう。健康を第一に考えながら、一歩ずつ前進していくことが大切です。
さらにキーワードで検索したい方はこちら!