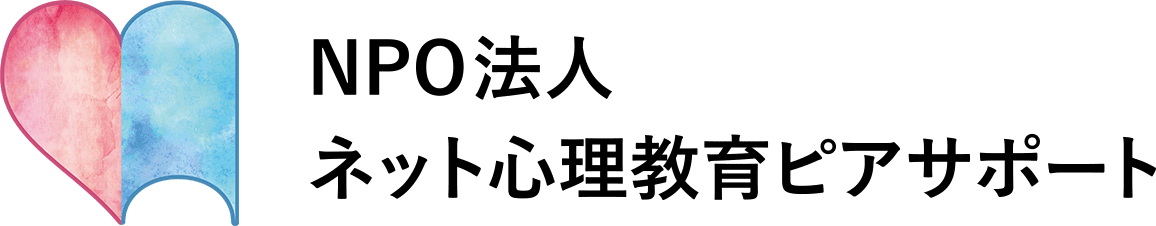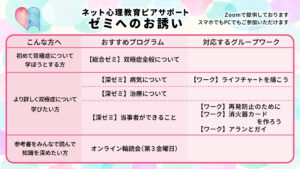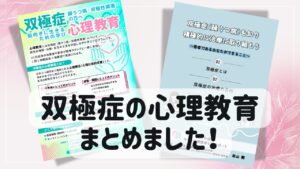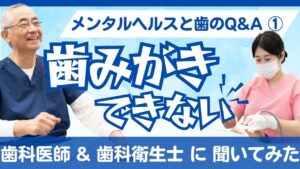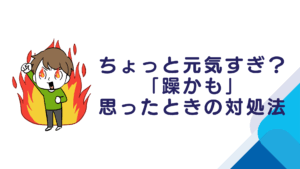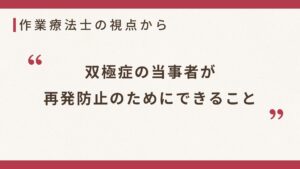中小企業の採用は「社運をかけた、たった一人の採用」──求職側と求人側、それぞれの視点でベンチャー企業を創業し株式上場に導いた元社長のリアルな視点

日本の企業の多くは中小企業です。そして中小企業側にとっての採用は、**たった一人の採用でも「社運をかけた決断」**なんです。
本記事では、かつてIT系ベンチャーを起業、経営し株式上場に導いた私の社長体験をもとに、求職者(働きたい人)と求人企業(雇う側)の両方の視点から、採用活動のリアルを紹介します。全ての求職活動に当てはまらないかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
【求人側(採用する側)の視点-1-】
中小企業が求人を出すタイミング
中小企業で求人が発生するタイミングは、大きく分けて次の2つ。
- 欠員が出たとき
- 事業拡大にともない人手が必要になったとき
短期の業務であれば外注や派遣社員で済ませますが、**正社員採用は「本気」**です。
人数が少ないぶん、一人の採用が職場の雰囲気や事業の成否に直結します。採用するのは通常一回の募集で一人です。
中小企業では求人活動をしても、ハーバード大卒みたいな履歴書的にピカピカの人は応募して来ません。求人側としては「応募してくれてありがとう」といった感覚です。結果、応募された人たちの書類をチェックすると、つつけばいくらでもほこりが出そうな感じを受けますが、採用する側もお互い様だし、実はあまり重要では無いです。
「たまたま会社が募集した時、たまたまそれを見て応募してくれた人の中から、募集要件に一番適していると思われる人『一人』を採用する。」これが中小企業の実態です。
あと、採用されるかどうかについてですが、選考のプロセスは学校のテストとは全く違います。学校では「苦手教科を克服しよう」なんて言われたと思いますが、企業は学校ではないのでそんなことは要求しません。減点主義ではないんです。
得意なものを見せてください。最高のあなたを見せてください。
採用プロセスの流れ
1. 採用の決定と求める人物像の整理
- 必要なスキル・資格
- 通勤できるかどうか
- 社風に合いそうか
🔎 よく「即戦力」が求められると言われますが、私が重視したのは「長く勤めてくれそうか」「成長してくれそうか」でした。
2. 募集方法を選ぶ
- ハローワーク
- 求人媒体・人材エージェント(数百万円ものコストがかかることもある)
- チラシ・地元媒体
- 関係者の紹介(高齢者採用で多め)
コストや人材の属性に応じて、適切なチャネルを選びます。
* 選考はいつ始まるか?
中小企業の選考は、「切り落とす」と「拾い上げる」が同時進行です。会社は求人に大きなリソースを割きますので、募集要件に合致しているか、だけでなく、募集要件には合わないけどこっちの仕事なら期待できる! なんて考えながら、あなたを見ています。
求職先から「募集した仕事じゃないんだけど、こんな仕事はどうでしょう?」と言われたことがある人もいるでしょう。それは会社の思いが込められた提案かもしれません。
【求職側(応募する側)の視点と戦略】
基本事項
提出書類、面接全体にわたって共通の考え方
何を開示するか:基本的には要求された事項だけ答え、何か付け加えたいことがある時のみ付け加える。例としては、アピールポイント、配慮してほしいことなど
ネガティブな情報を開示するかどうか:聞かれたら書けば良いし、聞かれなかったら書かなければ良い。ネガティブな情報を言わないのはウソをつくことになるのではないかというのは考えすぎ
書類選考で見られていること
1名の募集に対し、40名以上の応募があることも珍しくありません。40人分の応募書類をチェックすることはとても大変な作業です。
では、会社側は限られた時間でどこを見ているのでしょうか?
✔ 履歴書の見られるポイント
- 写真の雰囲気:明るいか・違和感がないか、(※容姿ではなく「雰囲気」)
履歴書では真っ先に見る、というか自然に目に飛び込んでくるのが写真です。こだわってください、重要です。
- 文章の簡潔さ:読みやすいか、不要なことが書かれていないか
- 空白期間の説明:正直に書く(育児・介護・病気・起業準備など)
- PCか手書きか:関係ないです (手書きが要求される職場は別かも)
💡 履歴書のフォーマットを自作すると書きたくない欄を削除できるメリットがあります。
✔ 職務経歴書で好印象な書き方:
- 応募先を意識してアピールポイントを書く
例えば、IT企業に「Excelで集計フォームを作成した」と書いても恐らく実績としては評価されない。書くなら「部署間の報告書を分析しExcelで一元管理できるようにした」とか
- 自慢話より事実ベースでの実績
- 直近から遡る形で記載
読む側は、まず直近何をしたか、何ができるかを確認し、その業務ができるようになった背景として、その前の職歴を遡るような感じで確認します
- 会社ごとに分け、最初に要約を入れる
- 「〇〇を頑張りました」より「〇〇を達成しました」
主観を排して書くこと(客観性がないと突っ込まれるか評価されない)
✏ 書類だけで「こやつ、できるな」と思わせる人は少ないので、差がつきます。
面接で問われるのは“人柄”と“誠実さ”
中小企業の面接は、堅苦しさよりも「この人と一緒に働けるか?」が重視されます。
面接は、試験ではなくお見合いです。「この会社嫌だな」と感じたら遠慮なく辞退した方が良いです。最初の印象は当たることが多いです。
特に圧迫面接を受けた場合、その会社への就職はお勧めしません。圧迫面接を行う会社は、「悪意があるのではなく対人スキルを確認するため」と言ったりしますが、裏を返すとその会社の業務ではそのような対人スキルが要求されるということです。
面接のコツは、「面接官がなぜこの質問をするのか?」を常に考えながら回答すること
同じ質問でも、会話の流れで答えは変わる
回答は冗長でないか、一言で終わらせていないか
質問内容を把握して答えているか(面接官の顔色でチェック)
面接官が見るポイント
- 入室の瞬間の雰囲気・明るさ
- 会話のテンポ・ノリ
- 一緒に働く姿がイメージできるか
- 真剣に働きたいという姿勢が伝わるか
- 柔軟な受け答えができるか
🎯 テンプレ回答の練習がバレてもOK。それは「準備してきた」証なので、むしろ好印象。
精神疾患について聞かれたら?
「健康状態に不安はありませんか?」という質問に対し、精神疾患のある方がどう答えるかは悩ましい問題です。
最初に、質問の意味を考える
今の状態を問われているのか、病歴を問われているのか?
過去何らかの病気にかかっていても、今なんともないなら、「ありません」でOK。
今までどうだったのかという質問なら、答えるポイントはこれ!
「自己管理できていること」をはっきりと伝えること。
🗣 例:「当時は大変でしたが、今は安定し自己管理もできています。御社にご迷惑をおかけすることはないと思います。」
病名を言うかどうかはケースバイケース。
たとえば「双極症」と言っても、面接官には通じないことが多く、面接時間が説明に費やされてしまうことがあります。
「以前の勤務先に確認しても良いか」と聞かれたら?
これは単なる脅しです。10年以上の期間で退職した社員について、他社から問い合わせがあったことは一度もありませんでした。
回答は「はい」一択です。
ここで「いいえ」と答えると前職で何かあったのか、辞める時揉めたのか、会社側から辞めさせられたのか、とか痛くもない腹を探られます。
私見では、こういう質問をしてくる会社はイジワルですね。
【求職側(採用する側)の視点-2-】
採用されたあとの「信頼の作り方」
採用された後が本当のスタートです。最も重要なのは、信頼を得ることです。最初に取り組むべき大切なプロセスです。
以下の事項はくだらないと思うかもしれませんがとても重要です。
初出社までにやっておくべきこと:
- 採用通知へのお礼メール
- 入社前の準備を確認
- 初出社には小さなお菓子を持参(気遣いが伝わります)
初出社で心がけたいこと「全社員があなたに注目している」
- 「何もわかりませんが、よろしくお願いします」の姿勢を忘れない
- 雑用でも笑顔で対応する(顔に出ます)
- 平社員、事務、パートの方には特に丁寧に接する(これから助けてくれるのはその人たちです)
- 最初の一週間の遅刻・欠勤は絶対NG!
⚠ 社内の人間関係は、自分の態度次第で大きく変わります。
【求人側(採用する側)の視点】
採用は「終わり」ではなく「始まり」
採用活動は、企業にとって「ゴール」ではなく「スタート」です。
新しく入った社員が早くなじみ、周囲と協力し力を発揮することこそが本当の成果です。
おわりに:両者の視点を知ることで、採用の質が変わる
求人する側・求職する側、それぞれに悩みや本音があります。
お互いの立場を理解することで、より良いマッチングと職場づくりが可能になります。
中小企業で働くことは、大きな責任とやりがいが同居する貴重な体験です。
自分の頑張りで、会社が変わる。これが中小企業ならではの働く楽しさでしょう。そして、楽しんで働ける人を会社側も探しているのです。
あなたが本当にフィットする職場と出会えることを願っています。
私の回想
私にとって、人事は非常に重いものでした。一人の新人の採用が社運を決しますから。
中小企業というのは一般的に無名ですし、福利厚生などは名の知れた大手企業よりもはるかに劣っています。恥ずかしながら、私の会社も就労環境は十分とは言えず、採用した従業員の毎月の給与、ボーナスをきちんと支給するのに精一杯で、血のにじむような苦労をしていました。それなのに、私は会社の目標達成を優先し、労働環境の改善は後回しだったと思います。
こんな会社でいいんだろうか? こんな会社を選んでくれるだろうか? そんなことを考えながら、いつしか1000人近い方と面接しました。多くの人を採用し、多くの人が去ってゆきました。それでも、こんな会社なのに創業から株式上場まで一緒に働いた、というか一緒に戦った仲間には感謝の言葉もありません。
会社を経営する中で、私がずっと気にしていたのは社員を知ることです。繰り返しになりますが、中小企業は社運をかけて採用活動を行います。しかし、書類選考と面接だけで人は判断できません。期待以上の人もいれば期待以下の人もいます。(これは採用した人の能力が低かったのではなく、単なるミスマッチ)期待した職能を発揮できなかった人、体調を崩す人…
それでも、採用した人は私たちの仲間なんですよ。苦労して採用した人が、その人の力を発揮するためにはどうしたら良いのかを徹底的に考えます。全てのことについて能力がない人なんてこの世の中にはいません。その人自身が知らないような才能、得意なこと、可能性を探します。苦手なことは何なのか、人間関係で何かつらいことはあるのだろうか、この部署の仕事は合わなかったようだけどこっちならどうだろうか…などなど試行錯誤の連続でした。
私は、その人が力を発揮して働ける場所を見つけだすこと、会社の成長を一緒に喜び合えること、これが中小企業にとっての採用活動のゴールだと思います。
少し余分な話を(あくまで個人の見解です)
いままで読んでいただいた方は、中小企業で働くって社員関係がベタベタして大変そうって思ったかもしれませんが、私の経験では大会社の人間関係も大差ないような気がします。ただし、求人広告などを見たとき「アットホームな会社です」というフレーズを見たら要注意。特に売り文句がない会社か、ガチでベタベタしている会社のどっちかです。
余談ですが、巷ではパワハラだとかブラックだとかの言葉が溢れかえっています。でも、真剣に経営をしようとすれば、そんなことはありえない。会社は会社の目標達成のために必要なリソースを調達し、管理者は部下のパフォーマンスを最大限にすることを考える。つまり、会社にしろ上司にしろ、従業員のパフォーマンスが発揮できない環境、つまり働きにくい状況を作るっておかしいんですよ。誰の得にもならないんですよ。はっきり言って好き嫌い、職位、感情を優先して動く上司は無能です。(まあ、私はセクハラ、パワハラをする側の人の心理が理解できていないんですけど。)
以上、ご参考になれば幸いです。
さらにキーワードで検索したい方はこちら!