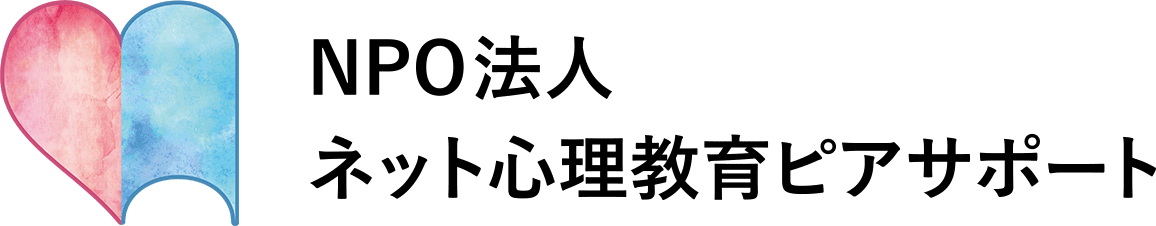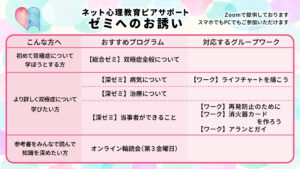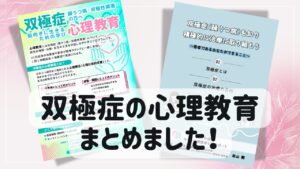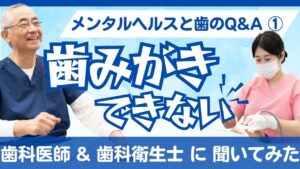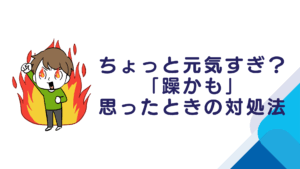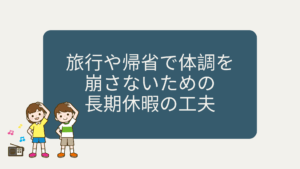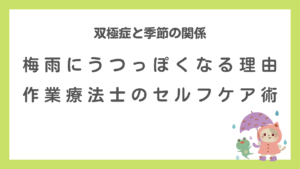作業療法士の視点から双極症の当事者が再発防止のためにできること
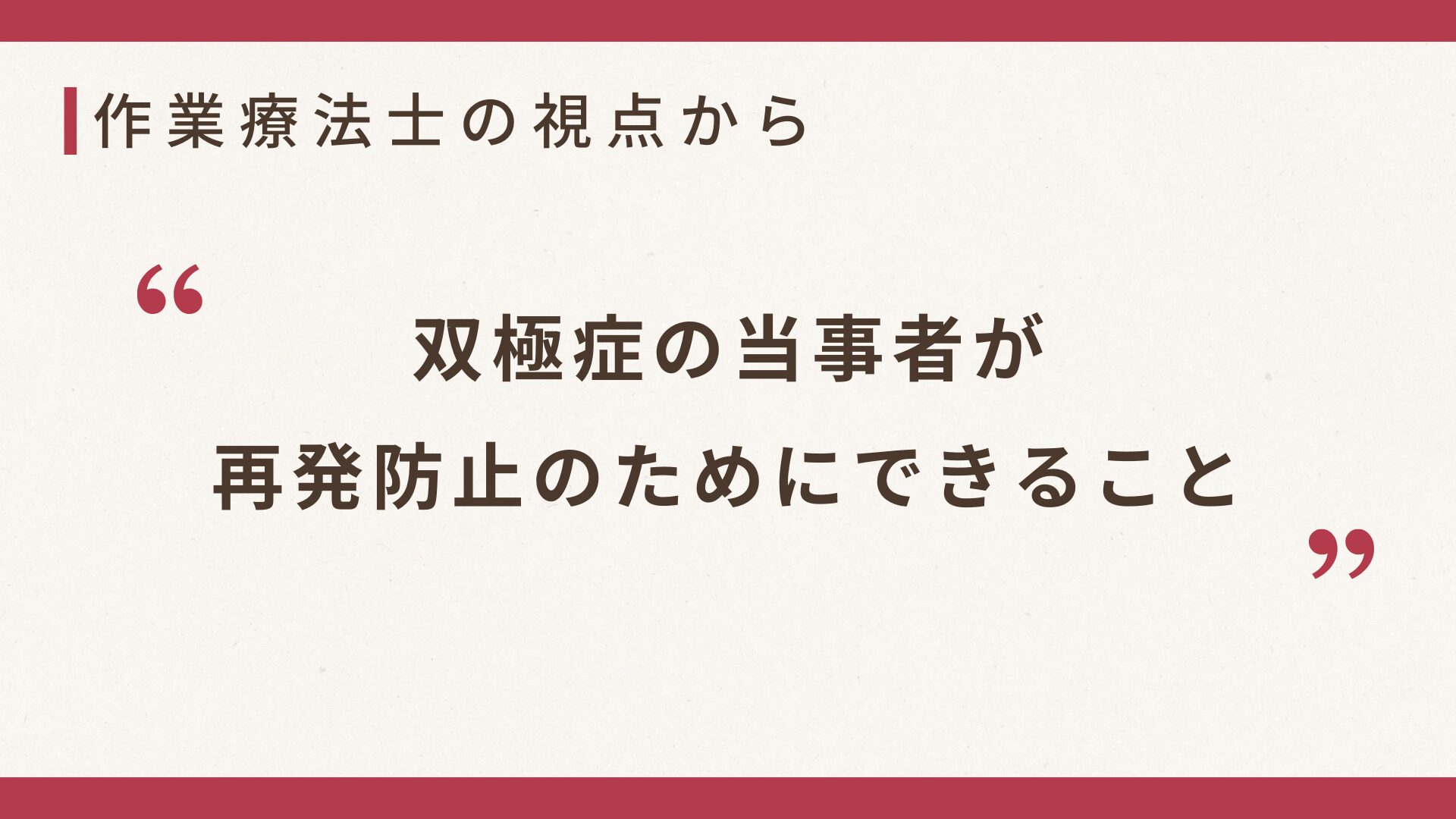
 おと
おと双極症Ⅱ型当事者、作業療法士のおとです。
梅雨は明けたものの、双極症の当事者にとって、体調を崩しやすい季節というのは変わりありません。
これ以上悪くなることは避けたいですよね。
また、症状が安定している「寛解状態」の方は維持し続けることが重要です。
今回のコラムでは、「再発防止のためにできること」をお伝えしたいと思います。
再発予防の主役は「あなた自身」です
双極症(双極性障害)は、気分の波が特徴的な病気です。
うつ状態と躁状態の間を行き来するのが辛い病気で、時にはあなた自身が気づいていない症状もあります。
躁やうつを繰り返し続けると、なかなか寛解状態にたどり着くまでが大変。
ですが、治療を主治医や服薬任せにするのはよくありません。
再発を防ぐ力は、「あなた自身が主役」ということを覚えてください。
医師や周囲の支援者に頼ることはもちろん大切です。
しかし、治療に積極的に関わる「あなた自身の姿勢」が、回復と気分の波の安定への大きな一歩になります。
再発防止のために、あなた自身ができること
① 病気や治療について正しく知る
「自分の病気について知ること」、病識を正しく持つことが大切です。
双極症とはどんな病気で、なぜ気分の波が起きるのか。
薬にはどんな働きがあり、なぜ継続して飲む必要があるのか。
知識がなければ、「今、自分が何のために治療をしているのか」が分からず、不安ばかりが大きくなってしまいます。
自発的に治療に取り組むことで、
「なんでこの薬が出されているのか主治医に聞いてみよう」
「病気のことについて調べてみよう」
と考えるきっかけになると思います。
正しい知識を身に着けるために、当団体のパンフレットも活用してくださいね。
② 生活習慣を整えよう
知識と同じくらい大切なのが、日常生活の習慣を整えることです。
・薬をきちんと飲む
調子がよくなってくると、薬の存在が面倒に思えることもあるかもしれません。
双極症の薬の「再発予防」とは、特定の症状を押さえるのではなく、症状が起こらない状態を維持することです。
服薬を自己中断すると、再発の引き金になり、症状が悪化する原因になるかもしれません。
主治医の処方通りに飲むことが大切です。
また、薬の増減を希望する場合は主治医とよく話し合ってくださいね。
・規則正しい生活
生活リズム、とくに睡眠のリズムは、気分の安定に直結します。
睡眠時間が短くなると、躁の傾向。
長くなると、うつの傾向かもしれません。
できるだけ決まった時間に起床・就寝したいところです。
睡眠時間だけでなく、日常のルーティンに大幅なズレがないことが、精神的な安定をもたらします。
・ストレスと上手に付き合う
完全にストレスのない生活は難しいですが、自分なりのストレス対処法を見つけましょう。
私の場合は、猫と遊ぶ、散歩をする、運動をする、ストレッチをするなどがストレス解消になっています。
また、「完璧主義(~しなければ)にならない」「周りに頼る」ことも大切です。
③ 気分の変化の【きざし】に早く気づく
再発の前触れには、必ずといっていいほど【きざし】があります。
小さい状態での【きざし】で対処できれば、軽い対応で早くよくなります。
一方、【きざし】に気づけなければ、治療は大掛かりなものになり、時間を要します。
どのような【きざし】があると、うつ、躁になりやすいか自身を観察してみましょう。
ノートや表にまとめておくのもいいですね。
【きざし】の特徴
・量の変化:普段から見られる行動が増える・減る
例:まくし立てるように話す、活動性や活力の亢進、睡眠の必要性の減少
・質の変化:普段は見られない、新たな行動や考えが出現する
例:普段穏やかなひとが過敏になりひとと言い争う、突然新しい物事に関心をもつ、精神活性物質を摂取する
一般的に、質の変化のほうがわかりやすいです。
おわりに
双極症を抱える生活は、決して簡単ではありません。
普段から自身の気分や波を把握することが再発防止のカギ。
あなたも知識を持ち、生活を整え、変化に気づけるようになる準備をしてみませんか?
大切なのは、「自分にできること」を焦らず、ひとつずつ続けることです。
無理のない範囲で、再発防止に取り組んでみてくださいね。
注意事項
※本コラムは、双極症に関する経験や知識をもとに執筆されたものであり、すべての方に当てはまる内容ではありません。個別の診断や治療については、必ず主治医等の専門家とご相談ください。
以上
さらにキーワードで検索したい方はこちら!